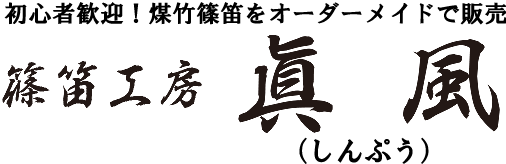新年おめでとうございます。
新年おめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。
今年は年明けから、動画を作っていました。
まずは古城・・・
懐かしい曲ですね?三橋さんの歌った名曲ですね。
次はひばりさんのリンゴ追分です。
いずれも、素晴らしい曲ばかりですが篠笛にもよく合って吹きがいのある曲です。
今後、このような日本の名曲を篠笛を吹いて偲んでいきたいと思います。
どうぞ、ご期待ください
無料篠笛セミナー
無料ZOOMオンライン篠笛セミナー
ZOOMオンライン篠笛セミナーをやることにしました。
ただし、私はZOOMに関してはまるきりの初心者。
1回目には13人の申し込みがありましたが、ZOOM内に入ることができない人が半数以上いました。
そこで、続けて今週もやることにしました。
そのご案内の動画が次のものです。
今からでも間に合いますのでご参加いただければと思います。
また、これからは定期的に初心者の為のZOOMオンラインセミナーを開催します。
もちろん、無料ですので遠慮なくご参加頂ければと思います。
星影のワルツ
次に私の青春時代の思い出として、50年前に流行った「星影のワルツ」を吹いてみました。
いままでも、ありありと思い出される曲で、昭和の時代を代表する曲の一つと思われます。
お楽しみ頂ければと思います。
お客様の感謝は一番
お客様の声
過日、送られてきたお客様の声を掲載します。
尚、プライバシー保護の関係上、お名前はイニシャルで表示します。
H・E 様より
本日10月4日 注文していた唄用(ドレミ調)七孔 六本調子 藤総巻き仕立て受け取りしました。
ホームページで拝見していた通りの、私の想像通りの商品で、大変満足しています。
篠笛を自己流で始めて二週間。
最初の一本を紅紫檀の八本調子を選んだのですが、やはり竹製のものが欲しくなり、増山様のものを選ばさせてもらいました。
甲音で苦労していたのですが、気持ちよく音が出てくれてうれしいです。
イロイロな曲にチャレンジしたいのですが、始めて未だ二週間ちょっとですので、基本からじっくりと練習していきます。
一年後に『コンドルは飛んでいく』を人前で披露できるが今の目標です。
一生大切にしたいと思います。
生きがいとは?
私の仕事の喜びはお客様からの「お問い合わせ」
次にお客様からの注文を頂き「楽しみ待っています」と言う言葉
そして「届きました」「期待通りの篠笛でした。」「これから大切に使います」
なんと嬉しい言葉ではないでしょうか?
これがあってこそ笛師みよりに付きます。
このようなことで今日もせっせと篠笛を作っています。
篠笛と尺八
第一は尺八、それとも篠笛?
私の家業は農家でした。つまりお百姓であったわけですが、なぜか本業よりも趣味の方にエネルギーを注ぐことになり尺八吹きになってしまいました。
しかし、決して本業を疎かにしていたわけではありません。
当時地域ではまだ誰もやっていなかった、ビニールハウスを導入してトマト・きゅうりの栽培、その後、軟弱野菜の水耕栽培、シイタケの菌床栽培、
・・と最後は南国のパッションフルーツの栽培等、次ぎ次とあやゆるものに挑戦し生活や子育ての為に必死に働いていました。
民謡との縁
そのような中にあっても。遠く60km離れた福島市(飯坂)まで尺八の稽古に約10年間通い続け、師匠に負けないくらいの技術を習得しました。
そして、相馬地方はもとより、東北でも数本の指に入る腕前になることができたと自画自賛しています???
震災後は仕事も尺八を吹くことも全くなくなり、最近思い出したように吹いています。
篠笛同様に多くの皆様に楽しんで頂ければと思いこれから少しづつユウチューブにアップしていきたいと思います。
お楽しみに・・・・
篠笛・忘れな草をあなたへ
外国製?
元々はヴォーチェヴォーチェ・アンジェリカの唄で、国内では「桜貝の歌」などと並ぶ抒情歌の不朽の名作ですね。
歌詞・メロディとも流麗で、今なおたくさんの人々が愛唱しています。
伝説
この歌には伝説的な由来がいくつもありますが、有名なのは次の伝説です。
ある若者が、ドナウの川辺で恋人のために珍しい青い花を摘み取ろうとしますが、崖から身を乗り出したとたん、足をすべらせて川に落ちてしまいました。
最期の瞬間に、彼は少女に向かって、「僕のことを忘れないで」と叫び、急流に飲み込まれました。
残された少女は、若者の墓にその花を植え、彼の最期のことばを花の名にしたといいます。
篠笛で吹くと
たくさんの有名歌手
この歌を日本ではたくさんの歌手が歌っています。
中でも有名なのが倍賞千恵子さんと菅原洋一さんですね。
レコードの売り上げでは菅原さんが一番とか?
篠笛の楽しみ
国内にはこのような心に響く唄がたくさんあります。
しかも、現代でも決して古さを感じさせることはなく、脈々と心に伝わってくるものがあります。
私の余生はこのような名曲を篠笛を吹いて楽しんでいくことになります。
これからも色々な日本的な素晴らしい曲を篠笛で紹介していきたいと思います。
お楽しみ頂ければと思います。
白い花の咲くころ 篠笛で歌おう
素敵な歌詞?
白い花が咲いてた
ふるさとの遠い夢の日、
さよならと言ったら
黙ってうつむいてた
お下げ髪
悲しかったあの時の
あの白い花だよ
・・・で始まるこの歌は寺尾智沙が作詞し、その夫である田村しげるが作曲しました。
ラジオ歌謡
1950年に岡本敦郎の歌唱によりNHKのラジオ歌謡で紹介されてヒット作となりました。
当時はテレビのなかった時代、ラジオから流れるこの曲に多くの青年や乙女たちは夢を現実のものと思いはせ歌い聴きいったようです。
篠笛を吹くコツ
篠笛を吹くコツについてお話しします。
まず第一には口や唇には絶対に力を入れないことです。
つまり、軽く吹くことです。
とかく音を出そうとすることに意識が集中してしまい口の周りに力が入ってしまうものです。
篠笛は軽く吹くほど全体的によく響き鳴ってくれます。
表現の方法は?
つまり、曲の表現法としてメリハリをつけて吹くことが求められます。
ここで大切なことは強く吹くことより、弱く吹くこと!!
このことの方がとても難しいです。
多くの人たちは強く吹いて強弱をつけようとしますが逆です。
弱く吹く、抜いて吹くのです。
篠笛の場合には普通に吹いても音量は十分にあります。
そこで軽くふんわりと柔らかく、ところどころを吹いてメリハリをつけるのです。
これがポイントです。
篠笛で歌おう 山のけむり
名曲を篠笛で
歌謡史が最も最盛期であった昭和20~30年代にはたくさんの名曲が作られました。
そんな中においても日本抒情的な曲で篠笛を吹いてもぴったりな曲がたくさんあります。
今回選んだ曲は「山のけむり」
山のけむり
作詞:大倉芳郎 作曲:八州秀章 唄:伊藤久雄で大ヒットした「山のけむり」
山の煙のほのぼのと たゆとう森よあの道よ. 幾年消えて流れゆく.
想い出の ああ 夢のひとすじ. 遠くしずかに ゆれている.
中々イメージに沿った演奏ができないのは毎度のことですが、ぜひ皆さんにも挑戦して楽しんで頂ければと思います。
篠笛で歌おう「長崎の鐘」
長崎の鐘
長崎の鐘と言えば真っ先に思い出されるのは歌手の藤山一郎氏。
しかしこれだけではありません。
実は長崎の医師である永井隆先生が自らの被爆体験を手記につづったタイトルだったのです。
そして、わが福島の誇る古関祐而先生が作曲、当時でも有名な詩人であったサトウハチロウ氏の詩が加わり、歌手の藤山一郎の美声のもとに大ヒットしたのが昭和の名曲と言われる「長崎の鐘」です。
篠笛で歌うには?
篠笛でメロディーを吹くのに大切なことは?別に難しいことはありません。
つまり、歌を唄うように吹けば良いのです。
しかし、声を出しながら篠笛は吹けませんので頭の中でしか歌うことができません。
では、どうすればよいのでしょうか?
曲のイメージ作り
全体的なメロディーが吹けるようになったなら、詩をよく読み理解し、
吐く息の量で強弱をつけ、メリハリをつけていきます。
あるいは各小節ごとに微妙な間の取り方を工夫をします。
これだけでも曲に表現力が出てきます。
節尻の音に注意!!
各小節の終わりの音には細心の注意が必要です。
音が切れたり、かすれたり、また音程が下がったり、とか・・・
これらによって自分のレベルがはっきりと示されてしまいます。
練習方法は?
最後の音を余韻を持たせて綺麗にする練習の方法はまず、自分のレベルを知ることにあります。
それには練習の時であっても常に録音やビデオカメラで録画再生をし、チックすることです。
そして、自分の演奏を修正していくことが大切になります。
これらを繰り返し繰り返し練習に取り入れていると、数ヵ月後には驚くほど上達します。
最初はそれなりでも続けましょう。
最初は自分の吹いている篠笛を聞くと嫌になってしまうものです。
私も人前で演奏活動をしなくなってから10年ほどになり、レベル低下に目に余るものがあります。
しかし、何とかしようとおもいつつ、恥を偲んで一人ビデオ練習をしています。
そして、これらの様子をユウチューブにアップしたのを1曲づつ紹介しているのです。
それでは動画をご覧ください。
今回もブログをご覧頂きありがとうございました・
篠笛で歌おう(桜貝の歌)
真笛
久し振りに真笛を作ってみました。
真子笛とは笛を作る竹材が真竹を使用しているので真笛と呼んでいるわけです。
調律が難しい!
真竹は篠竹に比べると節間が狭く、2~3個の節を抜く必要があります。
それにはまずドリルで節に穴を開け、そしてガリ棒で削り取る必要があります。
また、肉厚なため倍音が低くなりがちで調律が難しくなります。
音色は動画で
桜貝の歌について
桜貝の歌は昭和二十四年に発表されましたが、昭和十八年には完成されていたようです。
作曲の八州は鎌倉に住んでいた折、病で亡くなった恋人の面影を曲に託したと言われています。
作詞には当時逗子住まいの友人である土屋花情氏に委託、女性を虜にした名曲が生まれました。
うるわしき桜貝ひとつ 去りゆける君に捧げむ この貝は去年の浜辺に われひとり拾いし貝よ